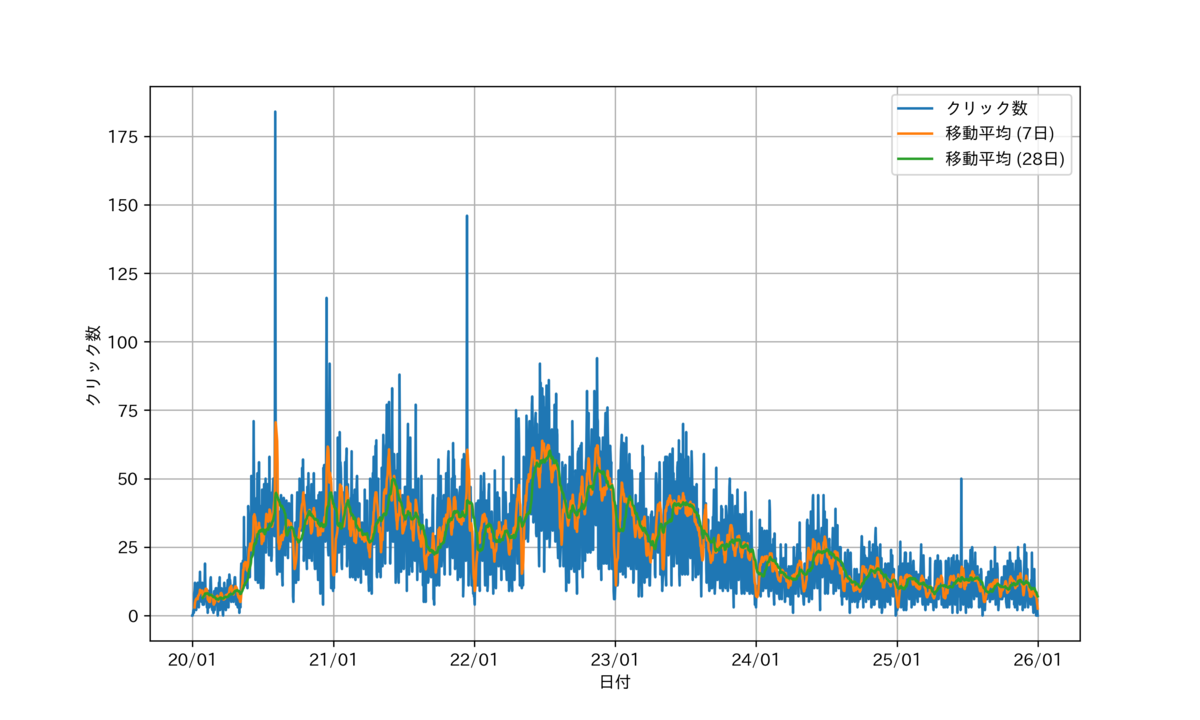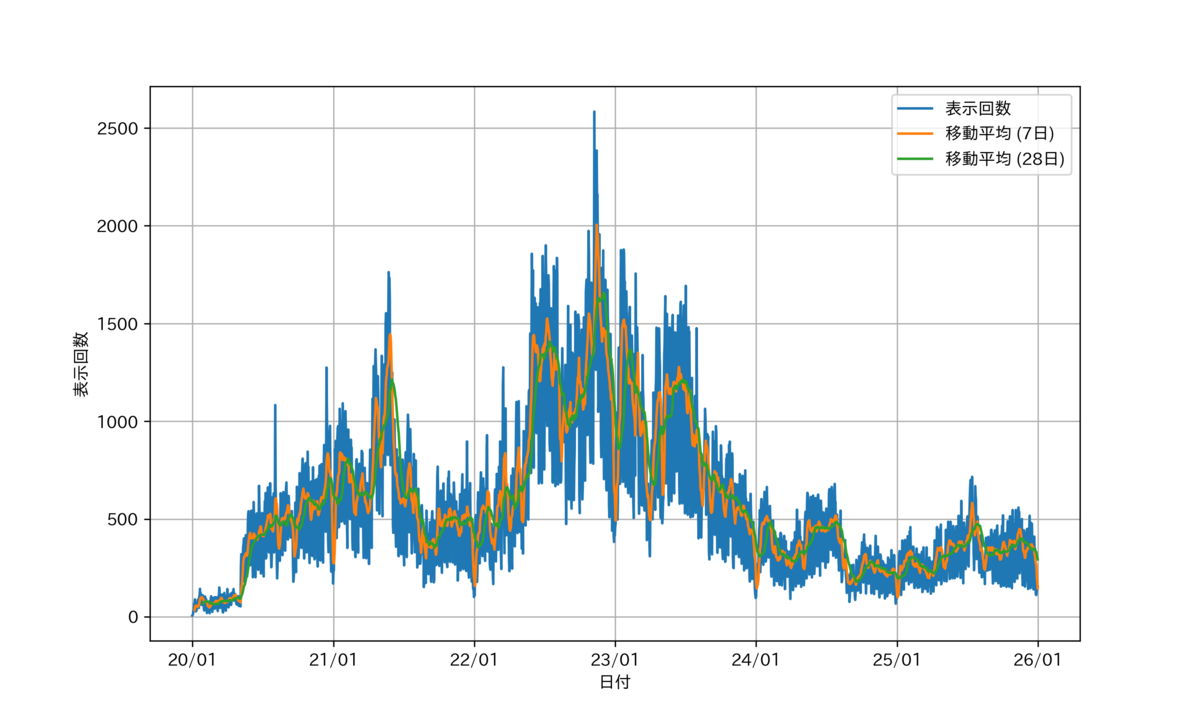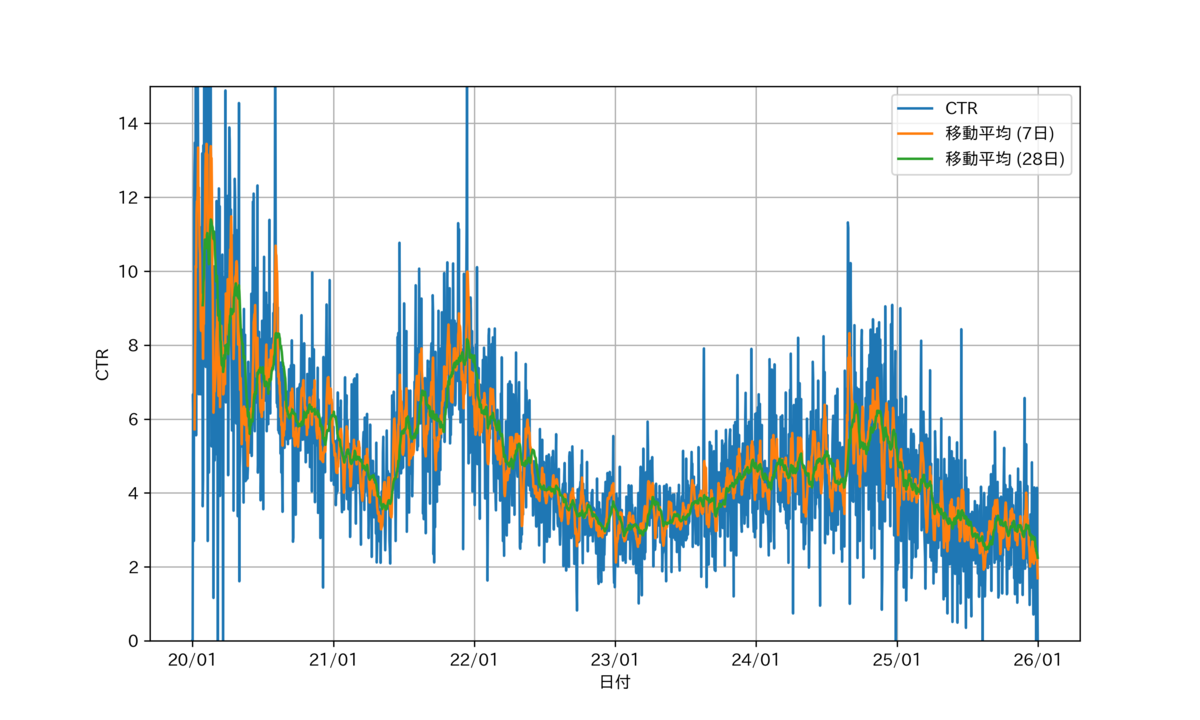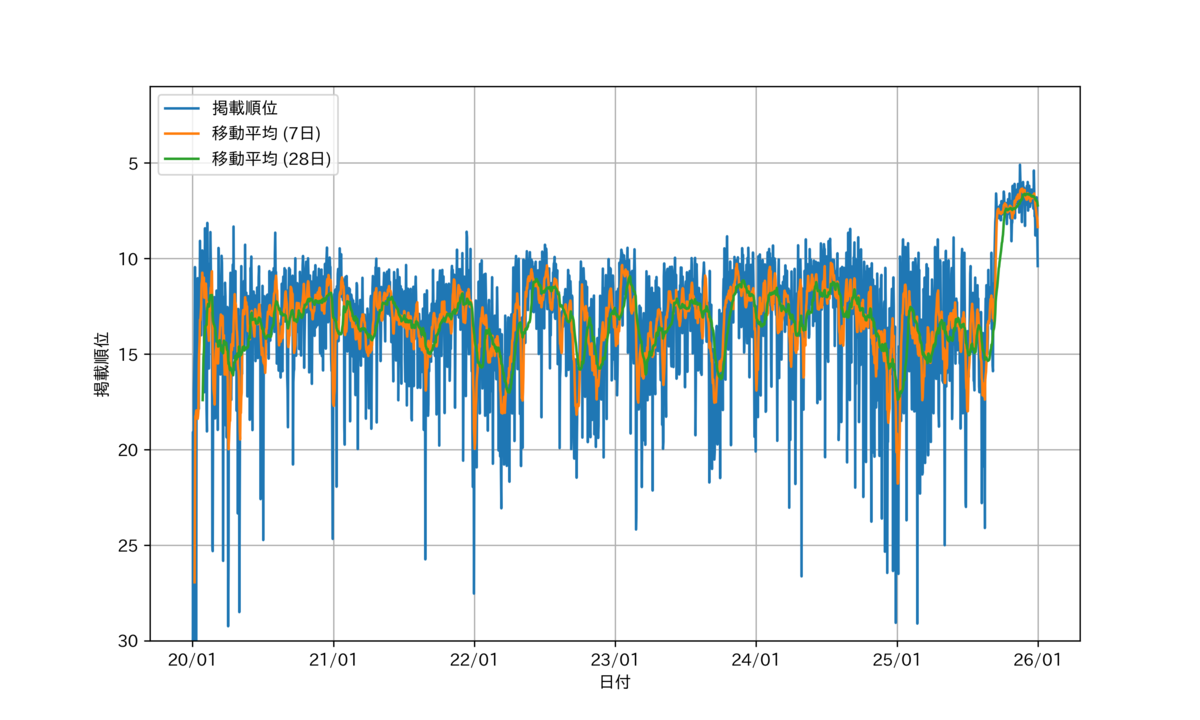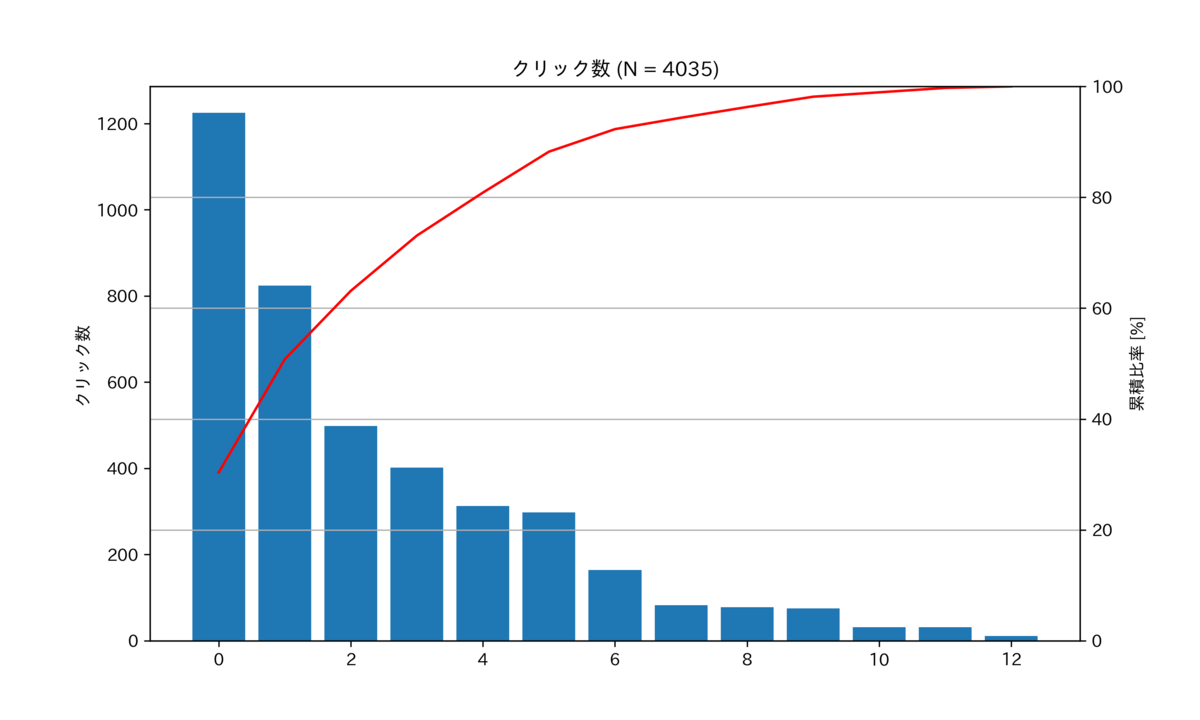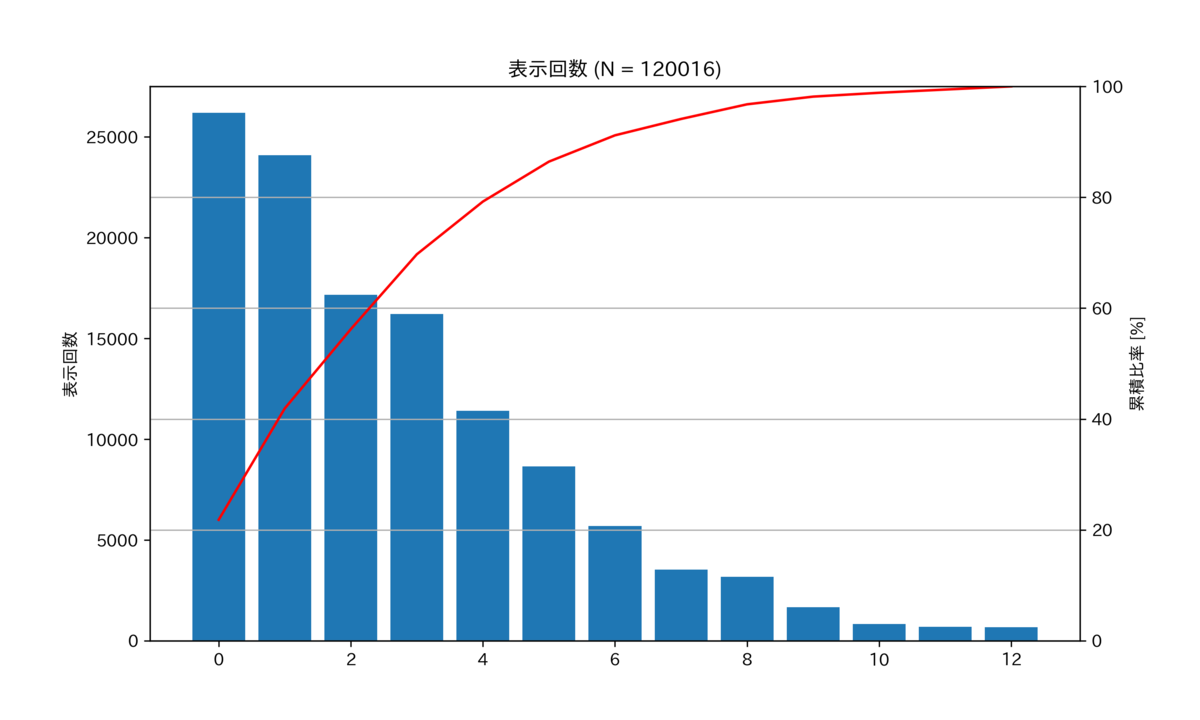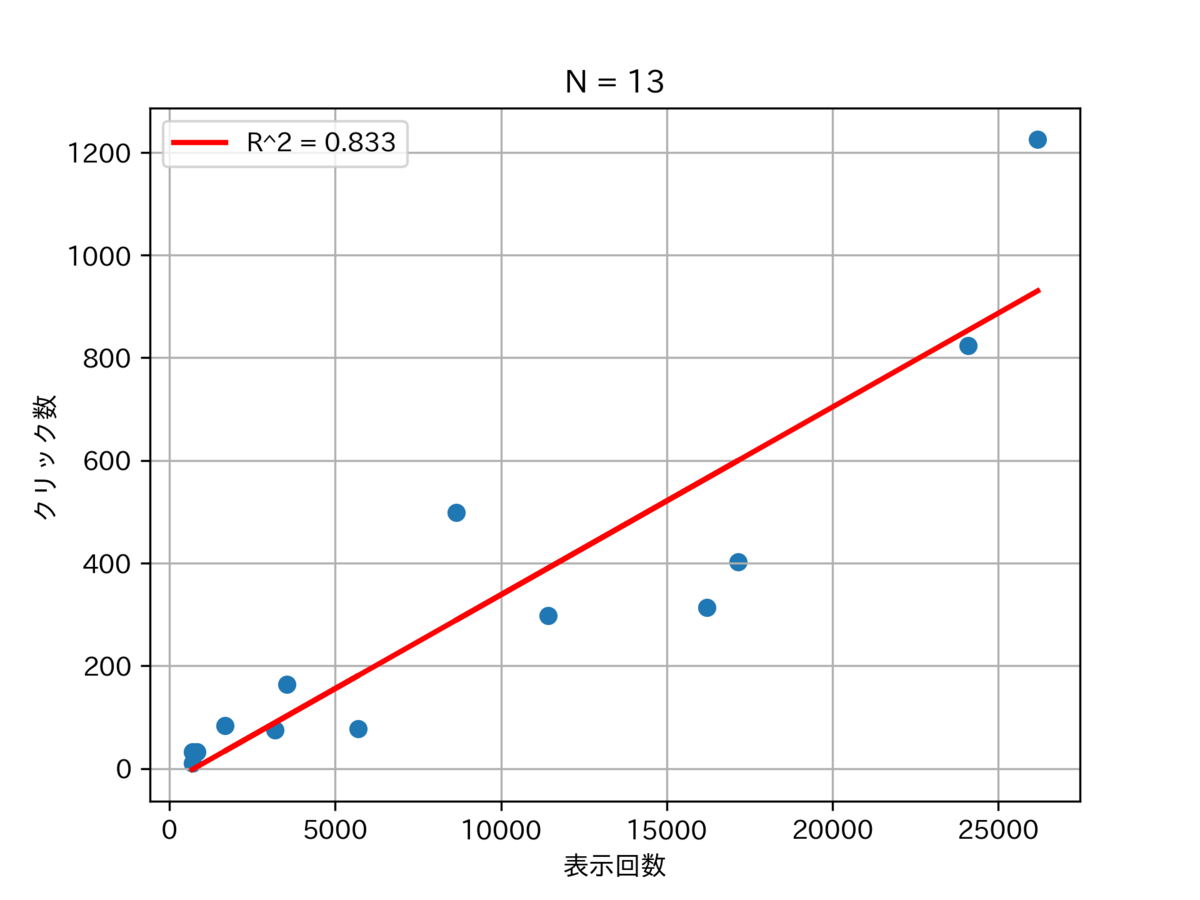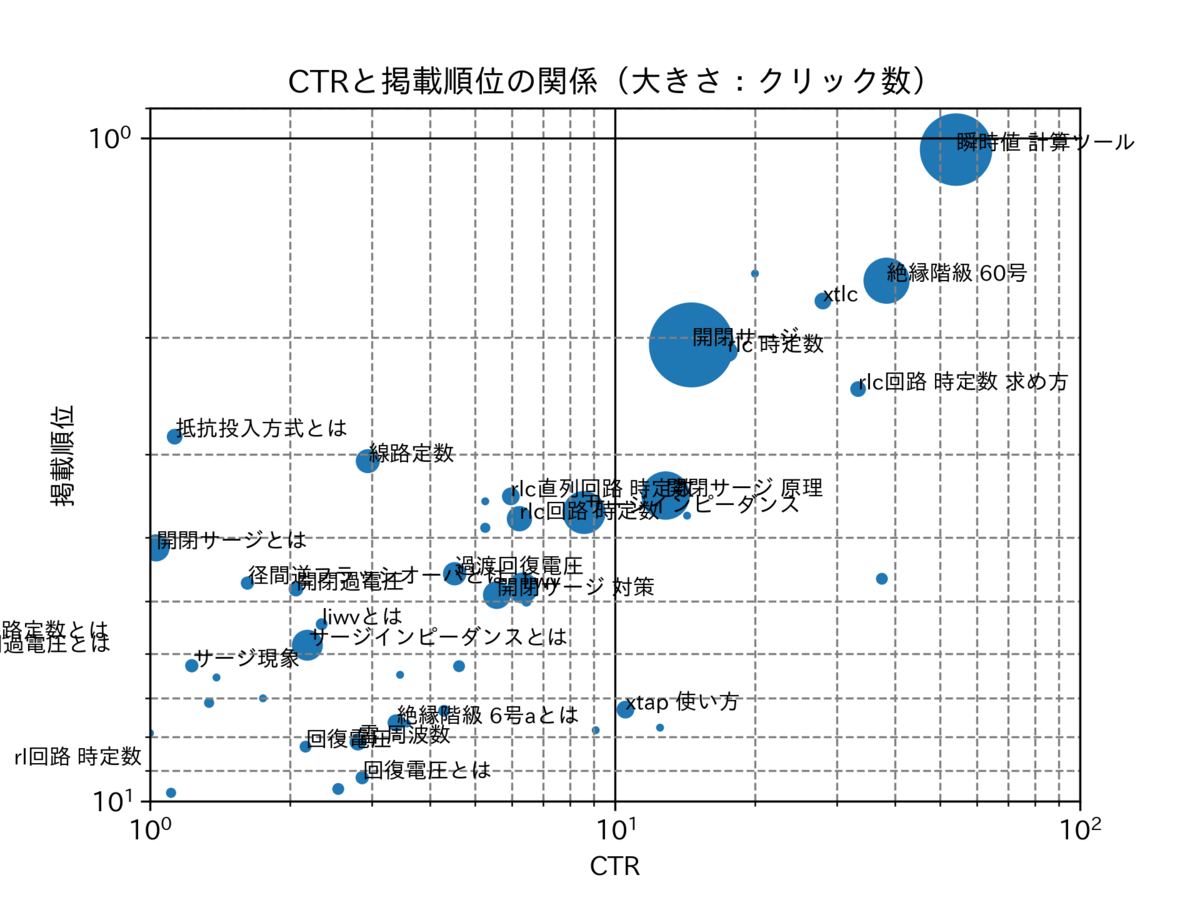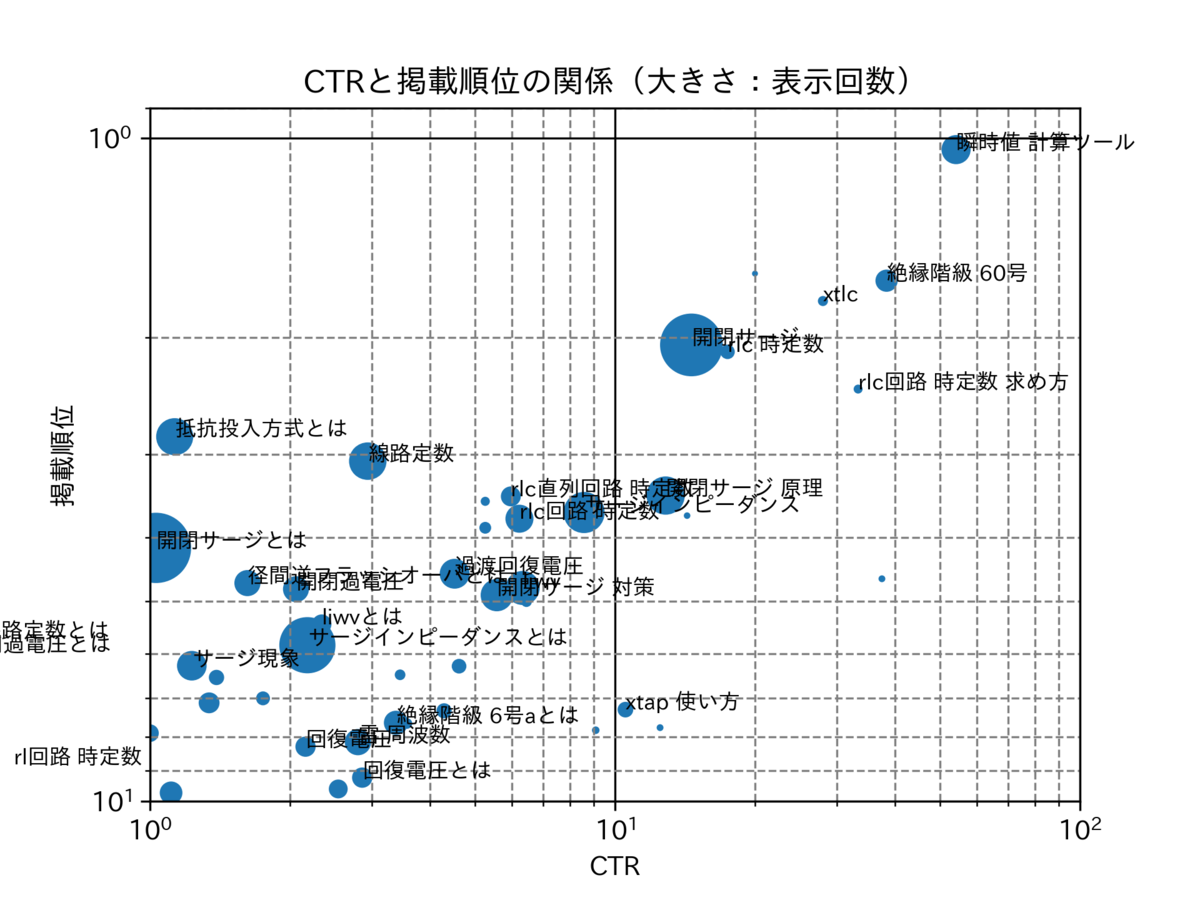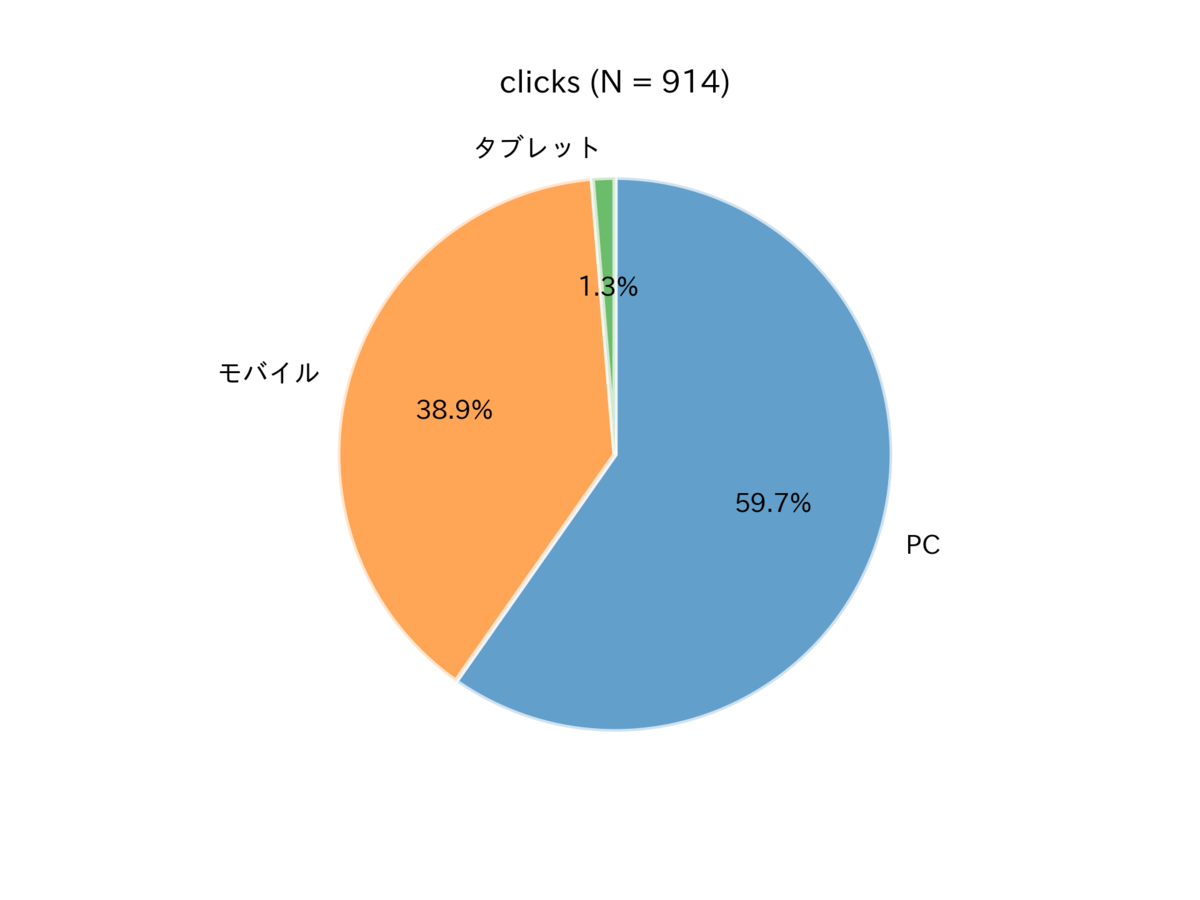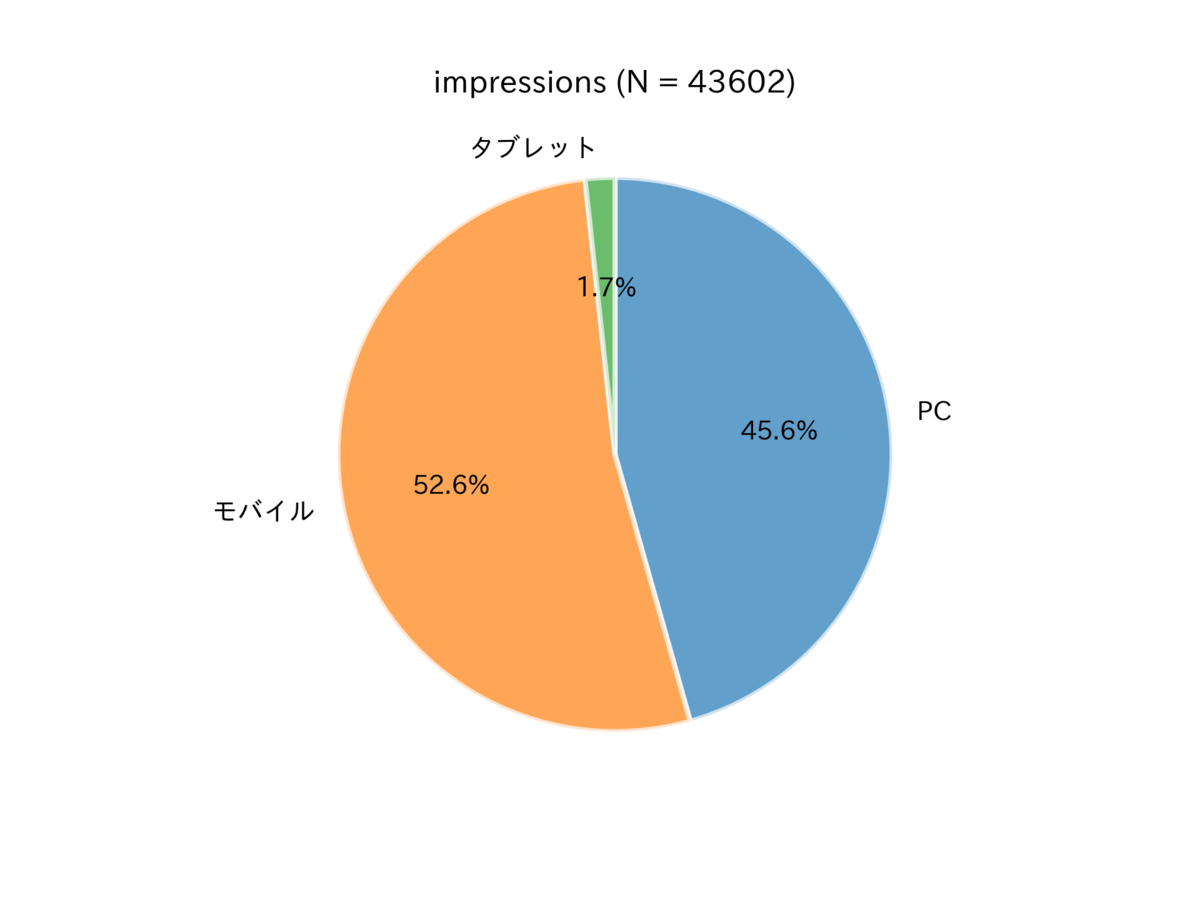『ドキュメント東京電力 福島原発誕生の内幕』(田原総一朗,文藝春秋,2011年7月10日)を読了した。
原子力導入の背景と「平和利用」の理想
日本が原発導入を決めた決定的理由は,1953年12月のアイゼンハワー米大統領の厳命であった。(p. 5)
原子力は,これまで大量の人間を殺害するための兵器であった。それを人類の平和と繁栄に役立つための有効な道具に転換する。それが原子力発電である
原子力の膨大なエネルギーを人類の平和のために使えるという理想は,今なお大きな魅力を持つものである。
「電力再編成」という言葉の重さ
電力再編成という言葉は,電力関係者たちには,電力の国家管理,電力国有化などというイメージに直結し,その言葉が使われた途端に,通産,いや国家と電力会社側との全面戦争になることが明白だったからである。その言葉を禁句にすることで,通産省と電力会社側は,部分戦争はくり返しながら,いわばデタントを保ってきたわけだ。(p. 22-23)
電力システム改革 2020 を経ても,「電力再編成」という言葉には過敏に反応してしまう。
電力の自立を守るという気概
「木川田さんの一生とは,国家を電力に介入させず,電力の自立を維持するための国家との戦いだった。そして,木川田さんは見事にそれをやってのけた」(p. 27)
今の電力業界に,電力の自立を維持するために国家と戦う気概のある者はいるのだろうか。
電力会社の体質と「巨大な下宿屋」
「電力会社とは,ようするに賄いつきの巨大な下宿屋みたいなものなのですよ。魚屋や肉屋,八百屋などが御用聞きに来る。その連中に,品質が悪いとか,高過ぎるとか尊大に構えて文句をいっていればよかった」(p. 30)
賄いつきの巨大な下宿屋という一面は,今もなお残っているように思える。
「巨大化しすぎた恐竜」としての電力会社
「巨大化しすぎた恐竜」
通産官僚たちは,電力会社のことを,こう呼んでいる。
恐竜は,中生代のジュラ紀から白亜紀に栄えた爬虫類で,巨大になりすぎたために,環境に適応できなくなって死滅したのだといわれているが,電力会社もまさにその巨大さゆえに身動きがとれなくなり,このままでは恐竜のように自滅するしかない,というわけだ。(p. 34)
通産省がなくなっても,恐竜としての電力会社は生き残った。この皮肉は重い。
事なかれ主義と官僚制の限界
「事なかれ主義で,身を挺するということを知らぬお役所仕事で,電力事業などできるわけがない。官僚には,電力を,国を,滅ぼすことはできても,絶対に発展はさせられない」
松永安左ェ門は,こうつぶやき,ひっそりとお茶をたてながら,国策会社・日発が,日本国と抱きあい,狂いの舞を演じつつ奈落にころげ落ちていくのをひややかに眺めていた。(p. 61-62)
事なかれ主義の官僚に,日本の未来を託すことはできない。官僚の描く未来像に踊らされてはならない。
自由競争とエネルギー政策の難しさ
「自由競争のエネルギーによってしか,企業の健全な成長はあり得ず,電力もその例外ではない」(p. 69)
エネルギー分野において自由競争だけでよいのか,今なお疑問が残る。
官僚の短期ローテーションと長期視点の欠如
「机上の数字あわせと,法律で規制することしか知らず,しかも,1,2 年でポンポンとポストがかわる無責任な官僚たちに,電力という,産業のいわば心臓部の主導権を奪われたら,日本は滅んでしまう,と木川田さんはことあるごとに力説していました」(p. 73)
短期間で異動する官僚に,超長期的な未来像を描くことは難しい。
電力会社の永遠の課題 : 借金と資金
「なんとかして,会社の借金を減らし,収入から得たお金を貯めて社内に自分の資金を多くしてゆくことがたいせつで,それがとりもなおさずにこれから東電という病体を健康体にし,りっぱなわたくしたちの会社とするいちばん大切な任務です」(p. 102)
借金を減らし,資金を増やすことは,電力会社にとって永遠の経営課題である。
政・財・官の外にいた電力会社
日本の政・財・官界は,政界は官界には強いが,財界に弱く,財界は政界には強いが官界に弱いという,グー・チョキ・パーの関係にある,といわれているが,電力会社は,グー・チョキ・パーの関係の外にいた。電力会社に対しては,政治家も,実業家も,そして官僚たちも頭が上がらなかった。(p. 104)
政財官の外にいたからこそ,電力会社は長らく我が世の春を謳歌できたのだろう。
国家会議構想と責任の所在
官僚主導による,上からの政策が危険であると同様に,木川田には,橋本の提唱する国民会議構想に危険な要素が多すぎるように思えてならなかったのだ。
「たしかに,国民,消費者の意見を聞く,いや尊重することは大事だとは思うが,原子力発電をつくり運営するのは電力会社なのであって,その責任のありかははっきりさせておかねばならない。国民会議というのは,一見民主的でよさそうだが,責任のありかがあいまいで,とんでもない暴走をしかねない」
木川田は,親しい新聞記者にこう洩らしている。(p. 145)
県民投票を経て原発再稼働が決まる現状を見ると,国民会議的な構造の危うさを思い起こさせる。
「一般受け」と地に足のついた経営
経営の現場以外からの発想は,一見かっこよくて一般受けをするが,とかく思いつきできめが粗い,地に足がついていない,と,木川田は,よく,身近な人間たちに語っていたようである。(p. 147)
かっこよさや一般受けだけを追っても,浮ついた施策しか生まれない。地道な努力こそが重要である。
集中型原子力基地と分散型構想
九電力が中心となってすすめてきた,日本の原子力開発は,過疎地に,巨大原子力基地を建設して 100 万 キロワット級の大型原子炉を何基も集中させる,という方式だった。それに対して通産省の新構想では,多くの小型原子炉を地域に分散させ,その地域で消費するエネルギーは,その地域でまかなう,という。この一点だけでも,現在の原子力開発の在り方に対する真っ向からの挑戦だといえる。(p. 209)
多くの原子炉を地域に分散させるより,拠点を集中させる方が合理的であると感じる。
国家介入を排除し続けた電力会社
電力会社は,GHQ という超権力によって日本発送電が解体され,九電力体制が発足して以来,電力国管の悪夢をふたたび甦らせまい,と,国家の介入を排除し,独立王国を築くために全精力を費やしてきた。東電の木川田一隆は,いわばその旗頭としてたたかいつづけてきたのだ。(p. 224)
電力を国家に委ねることは,二度とあってはならない。
「プラス・マキシマム」から「マイナス・ミニマム」へ
「経営政策会議では,かなり厳しい議論がかわされたようですが,結局は,木川田一隆の『プラス・マキシマムからマイナス・ミニマムへの転換』という言葉が決め手になって,“融和” という結論がひき出されたようです」(p. 225)
この転換は,経営方針の大きな方向変化を意味していたのだろう。
技術と組織が支える現場の力
依田*1はいった。たとえ官僚たちがどんな政策を考えようと,電力会社が時間をかけて開発してきた技術と,地域に根をはりめぐらせた組織なしには具現化もできなければ,運営もできないはずだという自信が,東電の融和策の裏付けになっているのだというわけだ。(p. 240)
机上の政策だけでは,現場の運営は成り立たない。技術と組織の蓄積こそが実行力を生む。
両超大国が,それぞれ原発事故を起こすことに,わたしは本書に登場する,日本原発の生きた歴史のような人物,橋本清之助(81年7月死去)が口ぐせのようにいっていた「ファウスト的契約」なる言葉を思い出していた。
ようするに,わたしたちは原子力という豊富なエネルギー源を得るのと引きかえに,一つ間違うと恐るべき災害を惹起するという潜在的危険性を抱え込んでしまったのだというわけだ。(p. 253)
恐るべき災害を経験してもなお,原子力の豊富なエネルギーを手放すことはできないという現実がある。

![AIビジネスチャンス 技術動向と事例に学ぶ新たな価値を生成する攻めの戦略(できるビジネス) [ 荻野調 ] AIビジネスチャンス 技術動向と事例に学ぶ新たな価値を生成する攻めの戦略(できるビジネス) [ 荻野調 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9275/9784295019275_1_2.jpg?_ex=128x128)
![AIビジネスチャンス 技術動向と事例に学ぶ新たな価値を生成する攻めの戦略(できるビジネス)【電子書籍】[ 荻野調 ] AIビジネスチャンス 技術動向と事例に学ぶ新たな価値を生成する攻めの戦略(できるビジネス)【電子書籍】[ 荻野調 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1663/2000015491663.jpg?_ex=128x128)

![人工知能はいかにして強くなるのか? 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ (ブルーバックス) [ 小野田 博一 ] 人工知能はいかにして強くなるのか? 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ (ブルーバックス) [ 小野田 博一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0012/9784065020012.jpg?_ex=128x128)
![人工知能はいかにして強くなるのか? 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ【電子書籍】[ 小野田博一 ] 人工知能はいかにして強くなるのか? 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ【電子書籍】[ 小野田博一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9366/2000004909366.jpg?_ex=128x128)


![時をかけるゆとり (文春文庫) [ 朝井 リョウ ] 時をかけるゆとり (文春文庫) [ 朝井 リョウ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2537/9784167902537.jpg?_ex=128x128)
![時をかけるゆとり【電子書籍】[ 朝井リョウ ] 時をかけるゆとり【電子書籍】[ 朝井リョウ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9466/2000002739466.jpg?_ex=128x128)


![GitLabに学ぶ パフォーマンスを最大化させるドキュメンテーション技術 数千ページにもわたるハンドブックを活用したテキストコミュニケーションの作法【電子書籍】[ 千田 和央 ] GitLabに学ぶ パフォーマンスを最大化させるドキュメンテーション技術 数千ページにもわたるハンドブックを活用したテキストコミュニケーションの作法【電子書籍】[ 千田 和央 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9336/2000016629336.jpg?_ex=128x128)
![GitLabに学ぶ パフォーマンスを最大化させるドキュメンテーション技術 数千ページにもわたるハンドブックを活用したテキストコミュニケーションの作法 [ 千田 和央 ] GitLabに学ぶ パフォーマンスを最大化させるドキュメンテーション技術 数千ページにもわたるハンドブックを活用したテキストコミュニケーションの作法 [ 千田 和央 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5705/9784798185705_1_130.jpg?_ex=128x128)